植毛するときはドナーを採取するため、後頭部を刈ります。術後は採取痕が残った頭皮がむき出しに。傷が目立たなくなり周りの既存毛が伸びてくるまではカモフラージュの対策が必要です。
手軽にできる対策のひとつであるヘアシートについて解説します。
ヘアシートとは?
ヘアシートとは聞き慣れない方も多いのではないでしょうか。
ヘアシートとは、部分的なウイッグ(かつら)のこと。自毛に結び特殊な接着剤で固定をして装着します。頭皮に貼り付けるわけではありません。これを後頭部に使うことで自毛植毛後の傷跡を隠すことが出来ます。
植毛後の後頭部はかなりインパクトのある見た目となります。毛が生えそろうまでの辛抱ではあるのですが、いかんせん悪目立ちするといけないので、多くの方はヘアシートを使い隠します。使用することで植毛をしたということを周囲にバレにくくする役目を果たしているのです。これがないと採取本数が多い場合、まず間違いなく植毛したことが周囲にバレてしまうでしょう。
ただ通常の装着方法だとシートの下部が接着されないため、絶対に安全とはいえません。そのため医師などと、より自然な装着方法を相談していきましょう。
ヘアシートの取り付け期間ですが、1-3ヶ月ほどは付けておいたほうが良いとされています。ちなみにヘアシートの裏側はメッシュになっており、通気性が確保されています。蒸れるのではと心配している方も安心ですね。
ヘアシートのメリット
ヘアシート最大のメリットは言うまでもなく、術後の傷跡を違和感ないように隠すことができるという点につきます。ただ全員がヘアシート装着を希望するかというと必ずしもそうではありません。後頭部の髪が長い場合は覆い隠すことが可能です。1000グラフト未満の施術であれば使用しない方が多いようです。2000グラフト以上であると希望者は増加の傾向にあります。
後頭部を隠すという目的であれば、ウィッグの使用が全てではありません。帽子やバンダナ、タオルなどでもカバーすることができます。ただ日常生活を送るうえで、支障をきたすこともあります。公的な場面に出席するとなると、帽子を被ったままでは難しい場合もあるのではないでしょうか。採取箇所が違和感なく隠れるまで、毛が生えそろうのに数か月かかる場合もあります。周りにバレたくないという思いがある場合はヘアシート装着を希望されたほうが無難でしょう。
ヘアシートのデメリット
ヘアシート装着を希望しない方も一定数おります。一番の理由は費用です。ウィッグのような物なので安くはありません。装着と取り外しを含めると、どこのクリニックでも3-5万円前後はかかります。
また毛が伸びていくにつれ、ヘアシートの位置の調整も必要となります。自分で調整するのは難しいので、その都度クリニックに行くことになります。諸費用・交通費・時間的な捻出なども余分にかかるというわけです。少しの期間ならば我慢できるという方はヘアシートによる対策にこだわらないようです。
次に多い理由として、ヘアシートを付けたからといって周囲に完全にバレないとは言い難いからです。ヘアシートは後頭部の既存毛にしっかり装着できるため取れる心配はまずありません。しかし、自毛の色とウイッグの色合いが完璧に合うことは稀です。また髪質で違和感を感じるかもしれません。刈り上げ範囲が小さい場合や隠す手段が他にある場合は、無理に取り付ける必要はないでしょう。
まとめ
初めて植毛するという方の場合、ヘアシート装着をオススメします。というのも、自らの判断で「大丈夫」と思っても、「やっぱり最初から付けるべきでした」と後で相談に来る方が一定の割合でいるからです。
何をおいても、植毛をお願いした信頼できる医師に相談し、決めることが重要だといえるでしょう。









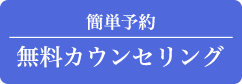
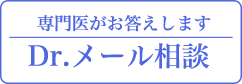
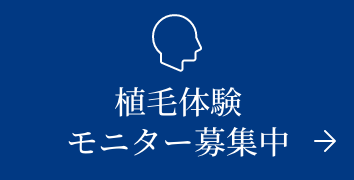
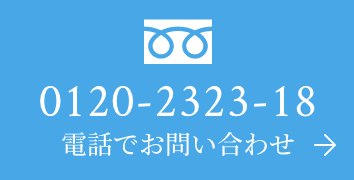
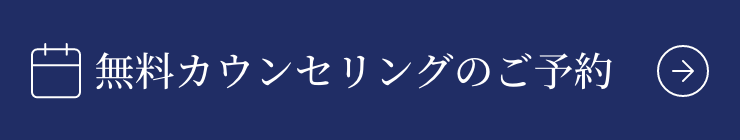
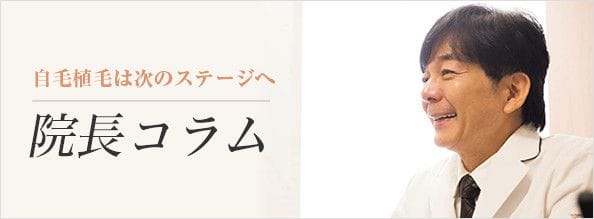


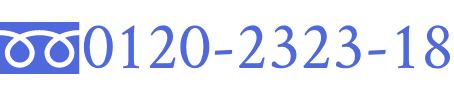
 髪の毛は毛穴から生えています。一つの毛穴には1〜4本の太い髪、1〜2本の産毛があり、皮脂腺、起立筋等と構成されています。この元からある自然な単位で株分けを行って、無毛の場所に再分配するというのがFUTの流れです。マイクログラフトでも1株に1〜3本という小さな株が使われていましたが、これは株のサイズが小さいというだけでFUの単位とはかぎりませんでした。
髪の毛は毛穴から生えています。一つの毛穴には1〜4本の太い髪、1〜2本の産毛があり、皮脂腺、起立筋等と構成されています。この元からある自然な単位で株分けを行って、無毛の場所に再分配するというのがFUTの流れです。マイクログラフトでも1株に1〜3本という小さな株が使われていましたが、これは株のサイズが小さいというだけでFUの単位とはかぎりませんでした。 しかし現代の自毛植毛治療を確立するパイオニアはなんと日本人の医師たちであったのです。1930年、笹川正男医師が特殊な針を使い、折り曲げた髪の毛を頭皮に挿入、きちんと定着したことを確認しました。1936年には慶応大学泌尿器科教授の田村一先生がアンダーヘアに単一毛で植え込むことに成功。自然に植毛するためには小さな株で植え込むことが良いという見方を発表しました。また1939年には奥田庄二医師がパンチ式植毛法の論文を発表しました。
しかし現代の自毛植毛治療を確立するパイオニアはなんと日本人の医師たちであったのです。1930年、笹川正男医師が特殊な針を使い、折り曲げた髪の毛を頭皮に挿入、きちんと定着したことを確認しました。1936年には慶応大学泌尿器科教授の田村一先生がアンダーヘアに単一毛で植え込むことに成功。自然に植毛するためには小さな株で植え込むことが良いという見方を発表しました。また1939年には奥田庄二医師がパンチ式植毛法の論文を発表しました。