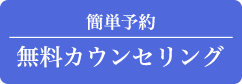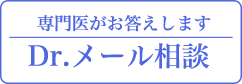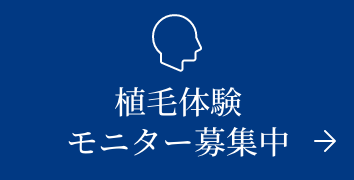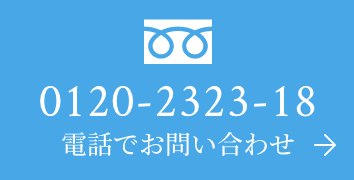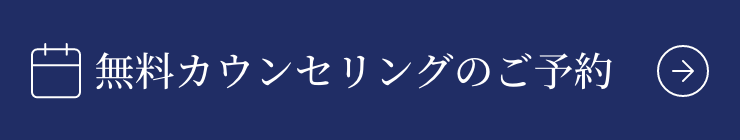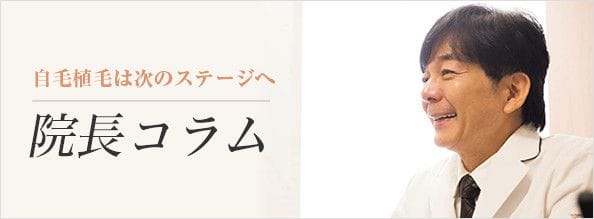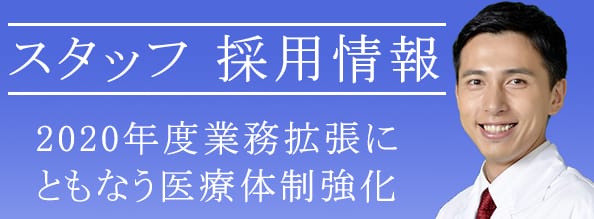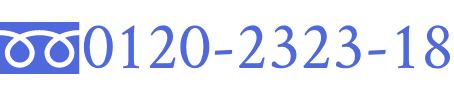フケとは? 誰にでも出るフケ。その正体は古くなった細胞です。 頭皮の表皮では常に新しい細胞がつくられ、やがて、はがれ落ちます。 この古くなった細胞がフケなのです。 フケの原因としては、ア…
ストレス過多の時代、それに関連した心身症が起こりやすくなっています。円形脱毛症もそのひとつです。動物実験では過重なストレスをかけると、半日程度で動物の毛が抜けた例があります。ただし、なぜ…
ダメージヘアとは? 何らかの原因で、頭髪が傷ついている状態を意味する言葉です。 では、そのようにして髪は傷むのでしょうか。 髪が傷む仕組みとは? 髪は、大きく3つの層からなっています。髪…
ストレスとは ストレスという用語は、もともと物理学の分野で使われていたもので、物体の外側からかけられた圧力によって歪みが生じた状態を言います。ストレスを風船にたとえてみると、風船を指で押…
①健康でいることが何よりの薄毛対策 現在、私たちの周りには薄毛改善のために様々な育毛剤などが発売されていますし、医療機関でも薄毛治療は多く行われています。 もちろん、薄毛を改善するために…