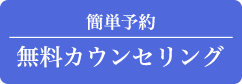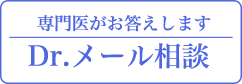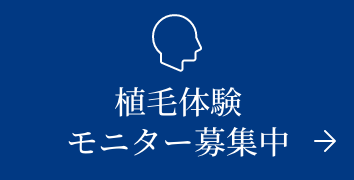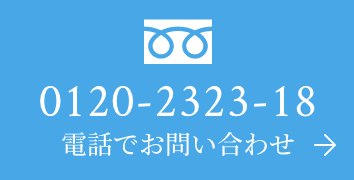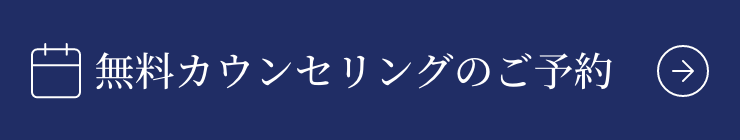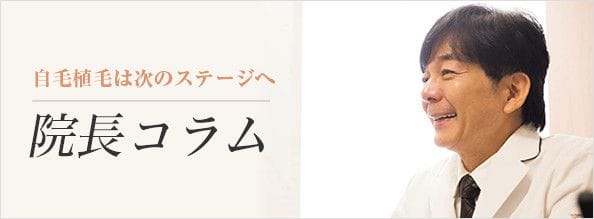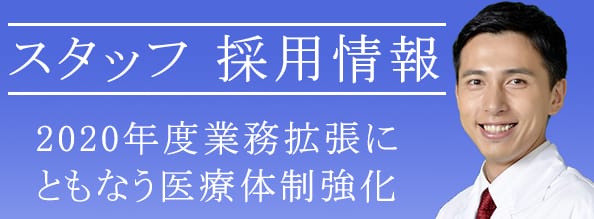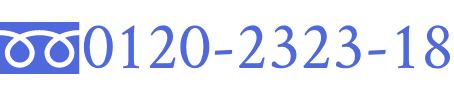水溶性ビタミンの続き ビオチン ビタミンB7とも呼ばれるビオチン。抗炎症物質を生成することによってアレルギー症状を緩和させる作用を持っています。ビオチンが欠乏すると皮膚炎や食欲不振、吐き…
水溶性ビタミン 水溶性ビタミンは体内で必要量を満たすまでほとんど尿中に排泄されないものです。必要量を超えた段階で急激に尿中排泄量が増大します。体内にビタミンを蓄積しておくことはできません…
人間が生きていくうえで欠かせないビタミン類は、発毛・育毛にとっても重要です。自毛植毛施術を受けたから終わりというわけではなく、施術後もきちんと髪に必要な栄養素を摂取すべきなのです。ただビ…
「これは薄毛の初期症状なのでは…」と思いつつも、まだ大丈夫なはず。と決めてかかり症状を悪化させている方があとを絶ちません。 薄毛の傾向が見られたら早めに専門の医院を受診し、医師の判断を仰…
植毛するときはドナーを採取するため、後頭部を刈ります。術後は採取痕が残った頭皮がむき出しに。傷が目立たなくなり周りの既存毛が伸びてくるまではカモフラージュの対策が必要です。 手軽にできる…
誰でも分かる自毛植毛の歴史の後編です。前篇では自毛植毛の歴史が古いこと、日本の技術が先進的だったこと、パンチグラフトからマイクログラフトに変わり、植毛は効率よりも美しさを求める方向となっ…